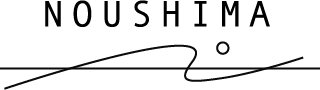そして、今年もまた、納島に「オゴ」の季節が巡ってきました。
「オゴ」とは、赤茶色をした海藻の一種で、刺身のツマや建築の補強材、あるいは農業用の敷材など、さまざまな用途に使われてきた自然素材です。
島の人たちにとってはとても身近で、けれど都市部ではあまり目にすることのない存在だと思います。
納島では、ただオゴを干して販売するだけではありません。
この島を未来に繋げるために、島の人たちがみんなで力を合わせて、必要な時に使えるお金をつくっておこう、という思いが込められています。
例えば、
「島で何かに挑戦したいと思った時」
「万が一、困ったことが起こった時」
そういう“いざという時”のために。
自分たちの手を動かしてしっかり準備をしておこう。
そんな感覚で、毎年この季節に、島の人たちが集まってオゴを干します。
都会で暮らしていた頃は、正直、そんなことを深く考えたことはありませんでした。
道がきれいなのも、水が出るのも、行政が何とかしてくれてると思っていたし、それが当たり前のように感じていました。
でも、島で暮らすようになって実感するのは、
「自分たちの暮らす場所を、自分たちで守っていく」という当たり前のすごさ。
たとえ人口が少なくても、手を動かし、知恵を出し合い、できることをやる。
その姿勢がこの島の基本です。
今年は本当に長く雨が続いて、正直どうなることかと心配もしましたが、、
なんとか綺麗に干し上がりました!
干している間も、わいわいおしゃべりしながら作業をしたり、お茶を飲んだり。
オゴ干しは、観光用にイベントとして行っているわけではないけれど、もしタイミングが合えば、見学したり、お手伝いしたり、一緒に体験することもできます。
何気ない作業のように見えて、その奥にはたくさんの学びがあります。
都会の喧騒からちょっと離れて、
潮の香りに包まれながら、手を動かし、島の暮らしを肌で感じてみませんか?